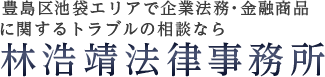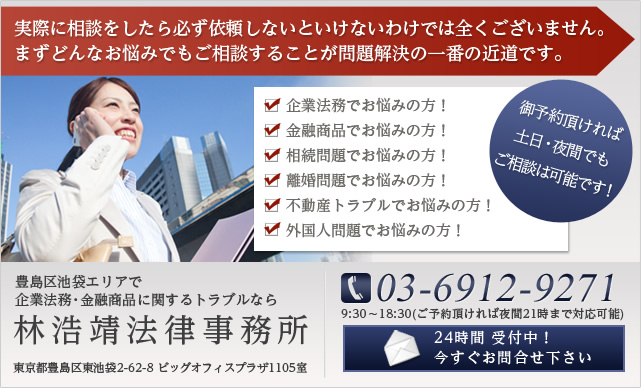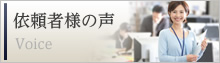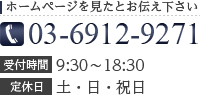所長ブログ
2017年6月30日 金曜日
[書評]勅使川原和彦 読解 民事訴訟法(有斐閣)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「読解 民事訴訟法」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
本書の著者は、早稲田大学法学学術院教授で、民事訴訟法をご専門とする。「本書は、『民事訴訟法』の講義において学生たちから受けた頻出の質問と、それに対する回答を集めたようなもので、いわば"民事訴訟法のFAQ"で」あり(はじめにⅰ頁)、いわゆる基本書のような網羅性はない。
民事訴訟というものは、ある意味不思議なもので、実は問題が起きない限り、民事訴訟法を知らなくてもこなせてしまうものである。民事訴訟法で議論する内容は、常識的に分かる手続に関する規定と、病理的な場面である論点が議論されている面があるからである。そのため、実務家でも手続的な感覚がない者も多く、本書は、そのような感覚を磨く上で有用と思われる。
何となく分かっているが、細かく詰めて考えようとすると混乱する問題の考え方を示しているからである。
また、「判決文を文言通り読むことの重要性」(はしがきⅳ頁)を本書は強調されている。言い換えれば、先入観を持って読まないということである。当たり前のことであるが、体系書や解説の記載で先入観を持って読むことは、気を付けないと起こし得ることであり、肝に銘じるべきところだと思う。
林浩靖法律事務所では、本書に限らず、常に研鑽を怠らず、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
投稿者 林浩靖法律事務所 | 記事URL
2017年6月24日 土曜日
誕生日
林浩靖法律事務所の弁護士の林です。
当職は、本日、41歳の誕生日を迎えました。
また1つ年をとりましたが、新たな気持ちで、皆様のお役にたてるように、日々研鑽してまいりますので、よろしくお願いします。
弁護士 林 浩靖
当職は、本日、41歳の誕生日を迎えました。
また1つ年をとりましたが、新たな気持ちで、皆様のお役にたてるように、日々研鑽してまいりますので、よろしくお願いします。
弁護士 林 浩靖
投稿者 林浩靖法律事務所 | 記事URL
2017年6月21日 水曜日
[書評]小西甚一 国文法ちかみち(ちくま学芸文庫)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「国文法ちかみち」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
本書の著者は、筑波大学名誉教授であり、本書は、一時代前の高校生向けの受験参考書である。
「はじめに」で、著者は「文法を忘れたまえ」(13頁)と言い切る。もっとも、その直後で、「忘れるためには、まず覚えていなくてはならない」(13頁)と述べているから、テクネ―としての文法は、無意識にできるようにならなければならないというのが、その真意だと思う。
そして、本書は、現代文と古文の文法がリンクするように論じられている。これは、島内景二電気通信大学教授が解説にて、「古代から現代まで、変化してやまない言葉とどう向き合い、変貌する文化を捉えるか」(543頁)という著者の問題意識を、高校生向けに示したものといえよう。
本書の「『ちかみち』とは、考え方の『すじみち』のことである」(545頁)。そして、「本書は、読者に文学と文化の学力を身に付けさせることを目指している」(547頁)。大学受験の先を見据えた受験参考書であった。
弁護士の仕事は、文書を書くということが大きな比重を占めます。林浩靖法律事務所では、法律に限らず、常に研鑽を怠らず、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
投稿者 林浩靖法律事務所 | 記事URL
2017年6月14日 水曜日
[書評]佐伯仁志 刑法総論の考え方・楽しみ方(法学教室LIBRARY)(有斐閣)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「刑法総論の考え方・楽しみ方(法学教室LIBRARY)」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
本書の著者は、東京大学教授で、ご専門は刑法である。刑法は、行為無価値論と結果無価値論の対立があるが、著者である佐伯教授は結果無価値論の立場にたつ。もっとも、その体系は、著者の師匠である平野竜一東京大学名誉教授に忠実で、責任構成要件を認める立場なので、判例・実務が採る行為無価値論からも、(若干注意して読むべき部分はあるが)違和感なく読むことは可能である。
本書は「読者の方に、刑法総論の基本的な考え方を理解していただき、自分で考えることの面白さをわかっていただく」いことを目標として」(はしがきⅰ頁)、法学教室で行われた連載をまとめたものである。
本書はいわゆる体系書ではないので、内容は網羅的ではないが、重要な論点は概ね網羅され、基本書をかみ砕いて説明したり、あるいは、隠れた前提や進んだ問題を明らかにするなど、副読本として使われることが想定されていると思われる書物であるが、刑法総論の知識だけでなく、「学説を評価する際にも、個々の見解の細かな違いを気にする前に、まず大づかみに違いを把握することが大事である」(222頁)、「判例研究においては、判例理論の検討だけでなく、実際の適用範囲を明らかにすることも、現実の法(Law in Action)を認識するという意味で重要である」など、学習上の注意点も示されている。
林浩靖法律事務所では、本書に限らず、常に研鑽を怠らず、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
投稿者 林浩靖法律事務所 | 記事URL
2017年6月 7日 水曜日
[書評]歴史教育研究会(日本)・歴史教科書研究会(韓国)編 [日韓共通歴史教材]日韓交流の歴史 先史から現代まで(明石書店)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「[日韓共通歴史教材]日韓交流の歴史 先史から現代まで」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
本書は、日本と韓国の学者と教育関係者の研究会が、集団で執筆したものであり、「先史から現代までの日本と韓国の交流史を、高校生や若者のための歴史の共通教材として書いたもので」あり(436頁)、「日韓関係史を正しく理解する」(5頁)ために書かれた通史である。
日本列島と朝鮮半島は、ともに中華社会の周縁であった。そのため、どうしても中国の動向の影響が、日本列島と朝鮮半島の関係に及ぶ。江戸時代の「通信使外交は、日本と朝鮮両国の努力により維持された」(154頁)ものであり、近代になり、西洋諸国の影響が及ぶようになると、その近代化の速度が、各国の命運を分けた。「日本にとって、日清戦争は清との戦争だけでなく、朝鮮民衆との戦争でもあった。」(186頁)そして、日本による植民地支配と第二次世界大戦の終結による朝鮮半島の解放、そして冷戦の影響による朝鮮半島の南北分断の固定化を経て、日本は日韓基本条約を締結し、韓国と国交を回復した。しかし、「日韓条約は、両国間の歴史認識に関する問題、領土問題、日朝修好問題などが提起される度に、問題の根源として振り返られている。」(312頁)
日本と一番近い外国である韓国との関係、それは好悪だけで扱える問題では決してない。そして、在日コリアンも多く、その基本的知識を有することは、社会人として当然、要求される事項である。
林浩靖法律事務所は、法律に限らず、そのバックグラウンドを押さえて業務しておりますので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
投稿者 林浩靖法律事務所 | 記事URL